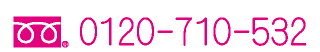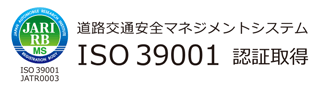静岡県 東名自動車学校のコラム
お客様に安心と自信、運転の達人になる道へのコラムをお伝えしていきたいと思います。
“大丈夫”が、一番危ない!―それがリスク・ホメオスタシス
あなたの運転、本当に「安全」ですか?
「この車は安全装備が充実しているから大丈夫」「スタッドレスタイヤを履いているから、雪道でも平気」そう思っていませんか?
実は、安全だと思ったその瞬間が、かえって危険な行動を引き起こすことがあります。これを「リスクホメオスタシス」と呼びます。
リスクホメオスタシスとは?
私たちの心には、無意識のうちに「これくらいのリスクなら許容できる」というリスクの目標水準が存在します。
たとえば、車に先進的な衝突回避システムや車線維持支援機能が付いていると、私たちは「安全になった」と感じます。
すると、この「安全になった」分を埋め合わせるように、無意識にスピードを上げたり、車間距離を詰めたりといった、よりリスキーな行動を取りがちになります。
その結果、安全技術が進歩しても事故がなかなか減らない、という逆説的な現象が起こるのです。
1. 安全は「技術」だけではない
リスクホメオスタシスが示すのは、真の安全は技術だけで実現できるものではない、ということです。
・道路が広くなったから、少しスピードを出す・冬用タイヤを履いたから、滑りやすい道でも急ハンドルを切る。
こうした行動は、安全対策によって生まれた余裕を、無意識のうちに「利益」(早く目的地に着く、運転を楽しむなど)に変えようとする心の働きです。
2. 運転の「心構え」を見直す
私たちは、車に乗り込むその瞬間から、常にリスクと向き合っています。「安全になったから大丈夫」ではなく、「安全になったからこそ、より慎重に運転しよう」という意識を持つことが重要です。
最新の安全技術は、私たちのミスを補うためのものです。過信して、その技術の限界を超えた運転をしてしまっては、意味がありません。
リスクホメオスタシスという心の働きを知ることは、あなたの運転をより安全にするための第一歩です。今一度、自分の中にあるリスクの目標水準について考えてみませんか?



リスク・ホメオスタシス理論とは
リスク・ホメオスタシス理論とは、人間が「許容できるリスクのレベル」を無意識に設定し、そのレベルを一定に保とうとする心理的な傾向を説明する理論です。
この理論は、カナダの心理学者ジェラルド・J・S・ワイルドによって提唱されました。
彼は、安全技術の向上や安全規制の強化だけでは、事故を減らす効果は限定的であると主張しました。
なぜなら、人々は安全性が高まったと感じると、その分を補うように、無意識のうちにより危険な行動を取るようになるからです。
交通事故における具体例
自動車の運転を例にとると、以下のような現象がリスク・ホメオスタシスによって説明されます。
- ・シートベルトやエアバッグの普及:シートベルトの着用が義務化され、エアバッグが標準装備されることで、運転者は「安全性が高まった」と感じます。
その結果、無意識にスピードを上げたり、車間距離を詰めたりする傾向が見られます。 - ・ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)の搭載:ABSは急ブレーキ時のタイヤロックを防ぎ、ハンドル操作を可能にする安全技術です。
しかし、ABSの性能を過信して、カーブを速い速度で曲がろうとしたり、雨天時に車間距離を短くしたりするドライバーがいます。
対策と課題
リスク・ホメオスタシス理論は、単に技術的な対策だけでなく、人々のリスクに対する意識や行動変容を促すことの重要性を示唆しています。
この理論に基づいた対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- ・リスク認知教育:安全技術の限界を正しく理解させ、過信を防ぐ教育。
- ・安全目標の共有:ドライバー1人ひとりが、安全運転という目標を明確に持つこと。
- ・行動経済学の応用:罰則強化だけでなく、安全運転を「得」と感じさせるようなインセンティブの導入。
リスク・ホメオスタシスは、安全対策を考える上で、技術的な側面だけでなく、人間の心理という複雑な要素を考慮する必要があることを教えてくれる重要な理論です。